世の中の高齢者は皆さんが思っている以上に転倒しているのです。自分の高齢の家族も他人事ではありません。
65歳以上の1〜2割が転倒している事が報告されています。✳︎東京都老人総合研究所長期プロジェクト研究報告書「中年からの老化予防総合的長期追跡研究」
つまり、高齢者の最大5人に1人は転倒しており、転倒した人の10パーセントが骨折しているのです。病院にも転倒して救急搬送される人が来て、骨折の手術をしているのが現状です。転倒による骨折から寝たきりになり、今までの生活が送れなくなっています。
骨折しやすい部位

高齢者の転倒で起こりやすい骨折部位
上腕
手首
背骨(胸椎と腰椎の移行部)骨盤よりもちょっと上
ふとももの骨
どっちにころんだ?
これは、転倒した方向で骨折した部位を推測できます。
横に転倒すると『上腕』『ふとももの骨』
前は『手首』
しりもちは『背骨』
まずはここを疑ってください。
骨折直後はどうなっているのか?
① 激しい痛み
② 腫れ
③ 動かせない
④ 外見の変形
⑤ 内出血
⑥ 冷や汗
が現れます。
転倒を目撃した時のあなたの行動
あなたは高齢の家族が左向きに転倒した場面を目撃します。
あなたは駆け寄ります。
声をかけると本人は左のふとももの痛みを訴えています。
足は痛みで動かすことができません。
痛みを訴えている部位はズボンを履いているため、ふとももを直接目で見ることは難しそうです。
ズボンの上からふとももを触ってみると、少し触っただけなのに激しい痛みを訴えます。
足を動かせるか本人に尋ねても、それができないことを本人から伝えられます。
当然、立ち上がる事はできずその場から動かす事ができません。
これはふとももの骨が折れていた場合です。
まとめ
転倒は高齢者ではよくあることです。
転倒した時に骨折しやすい部位は4つ。
①上腕
②手首
③背骨
④ふともも
折れた直後から激しい痛みを伴い、動かせなくなります。
高齢者は転倒しやすいものです。骨折しやすい箇所を覚えて焦らず対処しましょう。
高齢者が転倒した!救急車を呼ぶ判断と適切な初期対応
大切なご家族の転倒を目撃すると、「骨折していないか?」「救急車を呼ぶべき?」「今は大丈夫そうでも、後から問題が出ないか?」といった不安に苛まれるのは当然です。
この数分間の行動が、その後のご家族の安全と回復に大きく影響します。本記事は、40代以上の介護に関わる方へ向け、高齢者の転倒事故における「安全確保」「緊急性の判断」「骨折の確認」「経過観察」の最新かつ信頼できる情報(主に日本のガイドラインや統計データ)に基づいて、具体的な対応ステップを解説します。
高齢者の転倒:まず最初に行う「安全確保」と「状態確認」
『慌てて体を動かさず、安全を確保してから声かけと意識・状態の確認を優先する』ことが、転倒後の初期対応の基本です。
それは、転倒により骨折や重度の損傷を負っている場合、無理に体を動かすことで、症状を悪化させる危険性があるためです。
特に、高齢者の転倒で多い大腿骨近位部骨折(股関節の骨折)が疑われる場合、体動は避けるべきです。
具体例とデータ:
- 静止・声かけ
まずは落ち着いて近づき、意識と応答(呼びかけへの反応)を確認します。 - 無理に起こさない
ご本人が「起き上がれない」「動くと激しく痛む」と訴えたら、無理に抱え起こさず、毛布などで保温し安静を保ちます。 - 二次被害の排除
周囲に危険なもの(ガラス片、熱いものなど)がないか確認し、あれば取り除きます。 - 数字とデータ
消費者庁の調査報告書(2024年4月)によると、高齢者の転倒やつまずきによるけがは、打撲(43.9%)、擦り傷(32.1%)に次いで、骨折が30.7%と高い割合を占めています(出典2.4)。骨折のリスクが高いことを認識し、慎重に対応する必要があります。
まとめ: 初期対応は「動かさない」ことが最優先です。意識と痛みを確認し、二次被害を避けるための環境整備を行います。
救急車を呼ぶべき?転倒直後の「緊急性の判断基準」
救急要請の判断は迅速かつ正確に行う必要があります。
『結論』
意識や呼吸に異常がある場合、激しい痛みで動かせない場合、および頭部を強打している場合は、迷わず119番通報することが、救急搬送における重症度・緊急度判断基準に基づく推奨です。
『理由』
これらの症状は、命に関わる重度の外傷(例:頭蓋内出血)や、転倒が原因ではない脳卒中などの突発的な疾患を示している可能性があるためです。
具体例と複数の意見の比較
| 症状 (緊急性が高いサイン) | 対応 (救急車要請の判断) | 信頼できる情報源 |
| 意識がない/朦朧としている | 即座に119番通報 | 厚生労働省「救急搬送における重症度・緊急度判断基準」 |
| 呼吸が苦しい、胸を激しく痛がる | 即座に119番通報 | 外傷救急ガイドライン(意識・呼吸の評価を最優先) |
| 手足の麻痺、ろれつが回らない | 即座に119番通報 | 脳血管障害の徴候の可能性 |
| 頭を強く打ち、吐き気・嘔吐がある | 即座に119番通報 | 頭部外傷の重症化サイン |
| 変形がある、激痛で少しも動かせない | 即座に119番通報 | 骨折の可能性が極めて高いため |
| 軽度の打撲・擦り傷で元気がある | 医療機関に連絡の上、自己搬送を検討 | 日本老年医学会「高齢者の転倒予防ガイドライン」の初期対応 |
『まとめ』
意識や体の変形など、重症以上と判断した場合)は、救命救急センター等の三次救急医療機関での対応が必要となるため、迷わず救急車を呼びましょう。
骨折の可能性は?自宅でできる「確認ポイント」と医療機関への連携
緊急性がないと判断した場合でも、骨折の見逃しを防ぐことが重要です。
『結論』
転倒により「激しい痛み」「腫れ・変形」「動かせない」のいずれかがあれば骨折を強く疑い、患部を固定して整形外科を速やかに受診することが推奨されます。
『理由』
高齢者は骨粗鬆症の影響で、わずかな転倒でも骨折(特に大腿骨近位部、脊椎、手首など)を起こしやすいことが知られており、骨折を放置すると寝たきりなど重篤な結果につながるリスクがあるためです。
具体例と情報源:
- 確認ポイント: 触れるだけでも激痛が走る、患部が急激に腫れている、普段と違う方向に曲がっている(変形)がないかを確認します。
- 応急処置: 骨折が疑われる場合は、患部の上下の関節を固定し、動かさないようにします。これは、無理に動かすことで悪化するリスクを避けるためです(出典1.1)。
- 医療機関との連携: 応急処置後、かかりつけ医や整形外科に連絡し、転倒の状況や現在の症状を正確に伝えて、受診の手配を行いましょう。
- 【この情報は新しい?】 初期対応の原則(動かさない、安静、保温)は長年変わっていませんが、近年では救急隊到着までの時間短縮や、骨折後の早期手術の重要性がより強調されています。
『まとめ』
骨折の可能性を低く見積もらず、特に激しい痛みや変形が見られたら、医療機関への連携を急ぎましょう。
転倒後の「経過観察」の重要性と頭部外傷の注意点
転倒直後に症状がなくても、後から問題が出るケースがあるため、経過観察は欠かせません。
『結論』
頭部を打ったかどうかにかかわらず、転倒後48時間(特に6時間まで)は、意識レベルや体調の変化を注意深く観察する必要があります。
『理由』
高齢者は、軽微な頭部打撲でも、時間が経ってから慢性硬膜下血腫(頭蓋内出血の一種で、数週間~数ヶ月後に症状が出ることもある)を発症するリスクがあるためです。また、抗凝固剤(血液をサラサラにする薬)を服用している場合は、わずかな転倒でも出血リスクが高まります。
具体的な観察ポイント(信頼できる情報源)
| 観察項目 | 変化が見られた場合の対応 | 信頼できる情報源 |
| 意識レベル・反応 | 眠ってばかりいる、呼びかけへの反応が鈍い | 病院・介護施設の初期対応シート |
| 神経症状 | 手足に力が入らない(麻痺)、しびれ、ろれつが回らない | 日本老年医学会 外傷ガイドライン |
| 頭部症状 | 強い頭痛、吐き気や嘔吐、めまい | 病院・介護施設の初期対応シート |
| 局所の痛み | 打撲した部位とは違う場所(背中、股関節など)が痛む | 骨折の見逃し防止 |
『まとめ』
医療機関を受診しなかった場合でも、少なくとも転倒後48時間は、意識や体調の変化を注意深く観察し、異変があればすぐに再受診してください。
まとめと信頼できる情報源の提示
高齢者の転倒は、その後の生活の質を大きく左右する重要な事故です。
要点:
- 初期対応の基本:動かさず、意識と痛みの確認。
- 救急車判断:意識障害、呼吸異常、激痛、変形、頭部強打時は迷わず119番。
- 骨折:強い痛みや変形があれば固定し、速やかに整形外科へ。
- 経過観察:転倒後48時間(特に抗凝固剤服用者は)意識・体調の変化を注意深く見守る。
信頼できる情報源:
本記事の作成にあたっては、以下の情報源を参照しています。
- 厚生労働省:「エイジフレンドリーガイドライン」「救急搬送における重症度・緊急度判断基準」
- 日本老年医学会:「高齢者の転倒予防ガイドライン」「高齢者の外傷」
- 消費者庁:「高齢者の事故防止等に関するアンケート調査 報告書」
緊急時でも迅速に対応できるよう、ご家族のかかりつけ医の連絡先、および転倒時の緊急対応フロー(何をしたら119番か)をまとめたチェックリストを作成し、ご家族全員で共有しておきましょう。



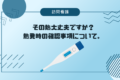
コメント